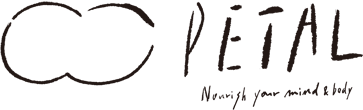2年越しの思いが叶い、杉本博司さんが設立した小田原文化財団の江之浦測候所にようやく伺うことができた。子どもが入場不可のため、なかなかチャンスが訪れなかったのだが、彼の書かれた本をこの2年で何度も再読しながら、色々と勝手な想像を膨らませていたのもある意味で特別な時間だった。娘が生まれた2017年に作られた江之浦測候所は、その後も作品の収集と拡大が計画され、そのアート細胞の増殖のような動きが、幼い娘の感性の成長と重なって見えて、また深く縁を感じずには居れなかった。
訪れてみて確かに感じているのは、その場所は私の想像力を遥かに超えた「時代村」ならぬ「時空村」だったということだ。「素晴らしい」や「景色がきれいだったね」という言葉では済まされないこの空間の不可侵性を、どのような言葉で形容すれば良いか、1週間ほど考えを熟成させていた。

江之浦測候所からの風景
訪れた日は、3月の末で明月門の桜や山の斜面を黄色に染める菜の花が咲き誇り、それはもう言葉をなくすほど美しかった。しかしながら何より自分の心を惹きつけたのは、古墳時代から近世に渡り日本中のあらゆる時代に、宗教的な役割、権威的な象徴となり崇められながら、いまこうして新たな運命に招聘され、一つの空間に集められた巨石の数々だ。巨石群が眠る六甲のふもと、御影の近くに育ち、石屋川を何度も渡りながら、そこに鎮座する苔むした岩や石と対話することを怠ってきたのだなあ、と深く反省した。
太古の日本人が石に祈り、石に魂を鎮め、樹木と同様に密接に関わり合ってきた石の声に、現代の私たちはどれくらい耳をすますことができているのだろうか。残念ながら、私も含めて現代人がしばらくじっと見ていられるのは墓石くらいではないか。物言わぬ石の存在を、物言わぬことをいいことに、ほぼ忘れかけていると言わざるを得ないような状況だ。

明月門、以前は根津美術館にあったもの
ここに来ると、自分のエネルギーを遥かに超えて、天上で響き合う鉱物、木、海、果ては宇宙という存在と芸術の星雲のような広大無辺な集合体に、塵のような自分の身体が反応し、名前もない人間が、ここにいることだけを只ひたすらに認識するような瞬間が訪れる。そういう人間の原感覚を呼び覚ます仕掛け(装置)を、杉本さんは作りたかったのかもしれない。
何より、杉本さん自身が合縁奇縁を繰り返しながら、10年以上の構想を経て一同に集められた作品が、決して散り散りに置かれた点ではなく、共鳴しながら、嬉々として新たな役目を果たそうとしていることが驚きなのだ。そのコンテクストはその場で丁寧に語られることも解説されることもないが、マテリアル自体が自ずとあなたに語りかけてくるだろう。
著名な寺院や神社が日本にも世界にも多数あるが、現代において祈りは形骸化しビジネスとなり、寺院の隅で魂を奪われた石を、幾度となく私は見てきた気がする。石もまた誰かの手によって魂を再び込めることで息を吹き返す存在であることを深く認識させられた。骨董もそうだが、縁ある茶碗であれ酒器であれ、その物自体が次の所有主を選んでいるとも思える。だとすれば、やはりここにある礎石も敷石も石橋も、ここに来ることを望んだのだろう。(小林秀雄さんが鎌倉の自宅で所有していたと言われる信楽の井戸枠は、持って帰らせていただきたかったが)

人の自然への眼差しの角度を変える仕掛けづくり
杉本さんはこの測候所をライフワークとし、全財産をつぎ込む覚悟で臨まれているという話を聞いた。家族にこの感動を伝えた時「杉本博司さんほど、今の日本人で、資本主義との絶妙な距離感をとりながら文化の復興を図っている芸術家が他にいるだろうか」という話になった。世界の資産家は、バンクシーやバスキアばかりを集めている場合ではないのである。
彼は現代における、能舞台の幽界と現世を結ぶ橋がかりのような存在なのだろうか。あの空間を自分のものだけにせず、全ての人に公開しアートを不得手と感じている人でさえも「自己との対話」に知らず知らずのうちに没入できる、彼曰く「天空を測候し、自身の場を確認する」ひと席を用意してくれたのだ。江の浦測候所は、お金だけでは成し遂げられない、彼自身が残りの人生を懸けて作り上げている芸術作品の最たるものなのではないか、とも感じる。

「日々是口実」の掛け軸
「昔は『増鏡』とか『今鏡』とか、歴史のことを鏡と言ったのです。鏡の中には、君自身が映るのです。歴史を読んで、自己を発見できないような歴史では駄目です。どんな歴史でもみんな現代史である、ということは現代のわれわれが歴史をもう一度生きてみるという、そんな経験を指しているのです。それができなければ、歴史は諸君の鏡にならない。」と語った小林秀雄の言葉を反芻する。
神不在の現在、一体芸術は何のためにあるのか。
この空間を訪ね、靄の中で手探りで生きる私たちへ向けられた、かすかな光を感じずには居れなかった。
訪れてみて確かに感じているのは、その場所は私の想像力を遥かに超えた「時代村」ならぬ「時空村」だったということだ。「素晴らしい」や「景色がきれいだったね」という言葉では済まされないこの空間の不可侵性を、どのような言葉で形容すれば良いか、1週間ほど考えを熟成させていた。

訪れた日は、3月の末で明月門の桜や山の斜面を黄色に染める菜の花が咲き誇り、それはもう言葉をなくすほど美しかった。しかしながら何より自分の心を惹きつけたのは、古墳時代から近世に渡り日本中のあらゆる時代に、宗教的な役割、権威的な象徴となり崇められながら、いまこうして新たな運命に招聘され、一つの空間に集められた巨石の数々だ。巨石群が眠る六甲のふもと、御影の近くに育ち、石屋川を何度も渡りながら、そこに鎮座する苔むした岩や石と対話することを怠ってきたのだなあ、と深く反省した。
太古の日本人が石に祈り、石に魂を鎮め、樹木と同様に密接に関わり合ってきた石の声に、現代の私たちはどれくらい耳をすますことができているのだろうか。残念ながら、私も含めて現代人がしばらくじっと見ていられるのは墓石くらいではないか。物言わぬ石の存在を、物言わぬことをいいことに、ほぼ忘れかけていると言わざるを得ないような状況だ。

ここに来ると、自分のエネルギーを遥かに超えて、天上で響き合う鉱物、木、海、果ては宇宙という存在と芸術の星雲のような広大無辺な集合体に、塵のような自分の身体が反応し、名前もない人間が、ここにいることだけを只ひたすらに認識するような瞬間が訪れる。そういう人間の原感覚を呼び覚ます仕掛け(装置)を、杉本さんは作りたかったのかもしれない。
何より、杉本さん自身が合縁奇縁を繰り返しながら、10年以上の構想を経て一同に集められた作品が、決して散り散りに置かれた点ではなく、共鳴しながら、嬉々として新たな役目を果たそうとしていることが驚きなのだ。そのコンテクストはその場で丁寧に語られることも解説されることもないが、マテリアル自体が自ずとあなたに語りかけてくるだろう。
著名な寺院や神社が日本にも世界にも多数あるが、現代において祈りは形骸化しビジネスとなり、寺院の隅で魂を奪われた石を、幾度となく私は見てきた気がする。石もまた誰かの手によって魂を再び込めることで息を吹き返す存在であることを深く認識させられた。骨董もそうだが、縁ある茶碗であれ酒器であれ、その物自体が次の所有主を選んでいるとも思える。だとすれば、やはりここにある礎石も敷石も石橋も、ここに来ることを望んだのだろう。(小林秀雄さんが鎌倉の自宅で所有していたと言われる信楽の井戸枠は、持って帰らせていただきたかったが)

杉本さんはこの測候所をライフワークとし、全財産をつぎ込む覚悟で臨まれているという話を聞いた。家族にこの感動を伝えた時「杉本博司さんほど、今の日本人で、資本主義との絶妙な距離感をとりながら文化の復興を図っている芸術家が他にいるだろうか」という話になった。世界の資産家は、バンクシーやバスキアばかりを集めている場合ではないのである。
彼は現代における、能舞台の幽界と現世を結ぶ橋がかりのような存在なのだろうか。あの空間を自分のものだけにせず、全ての人に公開しアートを不得手と感じている人でさえも「自己との対話」に知らず知らずのうちに没入できる、彼曰く「天空を測候し、自身の場を確認する」ひと席を用意してくれたのだ。江の浦測候所は、お金だけでは成し遂げられない、彼自身が残りの人生を懸けて作り上げている芸術作品の最たるものなのではないか、とも感じる。

「昔は『増鏡』とか『今鏡』とか、歴史のことを鏡と言ったのです。鏡の中には、君自身が映るのです。歴史を読んで、自己を発見できないような歴史では駄目です。どんな歴史でもみんな現代史である、ということは現代のわれわれが歴史をもう一度生きてみるという、そんな経験を指しているのです。それができなければ、歴史は諸君の鏡にならない。」と語った小林秀雄の言葉を反芻する。
神不在の現在、一体芸術は何のためにあるのか。
この空間を訪ね、靄の中で手探りで生きる私たちへ向けられた、かすかな光を感じずには居れなかった。