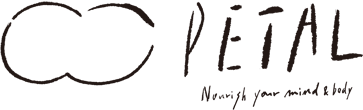焼きもののイノベーションが生まれる場所

美濃焼ときいて、私の頭の中に思い浮かぶのは、安土桃山時代に黄瀬戸、瀬戸黒、志野焼、織部焼といった大胆でありながら独自の美しさを確立し焼きものの革命を起こした古田織部の存在だが、美濃が生んだイノベーターは彼だけではない。戦前の1930年に可児市にある牟田洞古窯跡で、桃山時代に作られた志野焼の陶片を発見し、それまで瀬戸産と考えられていた「志野」が美濃産であることを証明するなど、日本の陶芸界に多大な影響を与えた陶芸家、荒川豊蔵もその一人だし、戦後の日本において「ものづくり」の急速な機械化と量産化の波が押し寄せる中で、岐阜、愛知、滋賀といった陶業地域に赴き、その土地に根づいた技術や自然を活かした血の通ったクラフトデザインの大切さを説いた、日根野作三というデザイナーの存在も忘れてはならない。
もともと陶土であるもぐさ土、製陶にぴったりの中性の軟水、高温の火力となる赤松樹木といった資源に恵まれた風土と、茶陶文化が繁盛した京都に近い場所にあることが功を奏したのか、美濃の多治見、土岐、瑞浪、可児をまたがる地域には日々の器から茶陶まで、常にその時代の新しい考え方を柔軟に取り入れる「遊びの余裕」と、それを着実に商売に結びつけていく「イノベーター気質」がどこかに残っている場所だという印象が私の中にある。

村上さんの制作された白磁の中国茶器
村上雄一さんに初めて展示会でお会いした時、彼の作っている作品の幅の広さとその数の多さに心底驚いた覚えがある。日常に使われるプレート皿やマカイ、紅茶に使われるティーカップソーサーやデザート皿、彼が今特に注力している茶壺、茶杯、茶海などの中国茶器、耐火性のある茶瓶まで、多種多様な器が制作されている上に、一つの形状ではなくさまざまなフォルムで展開されている。しかも、その一つ一つの作品としてのクオリティの高さ、何度も試作を重ねていくことで定まっていく機能美と装飾美を両立させたデザイン、その質に対する量の多さは、どう考えても、一人の陶芸家が生み出すことのできる範疇を超えていた。しかしながら、彼との会話の中で、制作が土岐で行われていること、彼自身が分業制による新たな焼きものの可能性を常に意識していることを聞き取ると、やはり、歴史的な背景や風土を兼ね備えた美濃という場所が村上さんを呼んだのだろう、と思わざるを得ない。きっと美濃には、量産型の生産と個人規模の生産の中間にあるような、分業制の生産を可能にする土壌があるのだろうと考えた。
土岐にある村上さんの工房へ

土岐市にある村上さんの工房
現代の焼きものイノベーターとも言える彼が今何を考えているのか、どのように制作を行なっているのか、その秘密は簡単には明かされずとも、そのヒントだけでも知りたくなった。以前から好きだった中国茶の話の花も咲き、彼のご厚意で、工房をカメラマンの水田秀樹さんと共に訪ねることができた。
村上さんの工房は、多治見駅から車で10分ほどの場所にある。一人で制作するには広すぎるのではないかと思われる工房の中には、再生土、地元の土、唐津の土、常滑の土、宜興(ぎこう)の朱泥、土鍋土などさまざまな陶土が積まれていて、制作する器とその目的によって土を変え、あるいは組み合わせることで最適な生地を作り出すのだという。「例えば、朱泥は土に含まれる鉄分の種類によって味が変化します。中国茶器の場合は、味が変わってくるから慎重になります。一方白磁の場合は味の変化がなく、お茶の持っている味をストレートに引き出します。」と村上さんは話す。

中国茶器に使われる朱泥
そんな彼が、自分個人の制作と並行しながら力を注いでいるのが、地元の業者さんの力を借りて、作家、業者、それぞれの強みを活かし合いながら分業制で茶器を量産していくプロジェクトだ。「作家ものは品質がグレーな面がありますがメーカーによる量産の品質は保証されています。そして割れてしまっても買い増せる。必然的に値段もお手頃になります。作家ものでもその辺りをクリアしたものを提供したいと思いました。」と話す彼に、技術面の不安はないのか、という質問を投げかけると「それはあります。でも、できないと思っていたことも、お互いの工夫で乗り越えられたりする。量産だから質が悪いとは限らず、むしろ、分業制にすることで質が上がることもある。中国には量産で美しいものは沢山あるけれど日本にはまだないから、それを成し遂げたい。美濃という土地にいるからこそ、それができるはず。」と熱のこもった答えが返ってきた。
陶器を作り出す陶土には恵まれていたが、磁器を制作するための陶石には伊万里のように恵まれていなかった美濃は、江戸時代の初め、陶土に珪石と長石を加え、工夫に工夫を重ねて磁器の生産に成功した歴史がある。資源や技術が足りないという状況においても、それを乗り越えるための創意工夫を重ねる精神がこの地には根付いていて、そのDNAを村上さんもまた受け継いでいるのかもしれない。

暖かな日差しが差し込む工房には様々な試作品が
「量産に必要な技術も、完全に機械ではなく結局は職人仕事なんです。そういった技術も、人の手によって成り立っている。分業制で業者さんが器の研磨をしたり仕上げてくれるのだけれど、縁の箇所の薄さが足りない時や滑らかな形状にしたい時は、自分が仕上げたりする。それでもやっぱり、最初から最後まで自分で制作するのとは時間の掛け方が全く違う。」完全機械生産ではない焼きものの制作において、機械を使いこなすのもまた人。そして技術力とセンスが問われる。当たり前のようなことだけれど、村上さんに言われて、改めてはっとさせられた。
分業制が成功すれば、今後人材の確保と育成に繋がり、ひいては美濃の町興しに繋がるかもしれない。「そうできるように、今色々な人と知恵を出し合いながら、なんとか街を盛り上げるために奮闘している。でも、まだまだ人材は不足しているし、日本で使われる陶磁器も海外製が多くなっているし、美濃にある土を作るための工場も老朽化を迎えて設備投資が必要だし、戦後から今にかけて積もった色々な問題に直面している。10年後にどうしようか?と話しても、もう間に合わないと思う。」その話を伺って、自分が関わっていた醤油の木桶もまた絶滅危機であることを思い出す。先日伺った嬉野の茶農家さんが抱えている人材問題にも共通するところがある。日本の伝統工芸、伝統食、さまざまなものが存続か断絶か、まさに岐路に立たされている。

釉掛けを待つマカイ、なます皿

美濃焼ときいて、私の頭の中に思い浮かぶのは、安土桃山時代に黄瀬戸、瀬戸黒、志野焼、織部焼といった大胆でありながら独自の美しさを確立し焼きものの革命を起こした古田織部の存在だが、美濃が生んだイノベーターは彼だけではない。戦前の1930年に可児市にある牟田洞古窯跡で、桃山時代に作られた志野焼の陶片を発見し、それまで瀬戸産と考えられていた「志野」が美濃産であることを証明するなど、日本の陶芸界に多大な影響を与えた陶芸家、荒川豊蔵もその一人だし、戦後の日本において「ものづくり」の急速な機械化と量産化の波が押し寄せる中で、岐阜、愛知、滋賀といった陶業地域に赴き、その土地に根づいた技術や自然を活かした血の通ったクラフトデザインの大切さを説いた、日根野作三というデザイナーの存在も忘れてはならない。
もともと陶土であるもぐさ土、製陶にぴったりの中性の軟水、高温の火力となる赤松樹木といった資源に恵まれた風土と、茶陶文化が繁盛した京都に近い場所にあることが功を奏したのか、美濃の多治見、土岐、瑞浪、可児をまたがる地域には日々の器から茶陶まで、常にその時代の新しい考え方を柔軟に取り入れる「遊びの余裕」と、それを着実に商売に結びつけていく「イノベーター気質」がどこかに残っている場所だという印象が私の中にある。

村上雄一さんに初めて展示会でお会いした時、彼の作っている作品の幅の広さとその数の多さに心底驚いた覚えがある。日常に使われるプレート皿やマカイ、紅茶に使われるティーカップソーサーやデザート皿、彼が今特に注力している茶壺、茶杯、茶海などの中国茶器、耐火性のある茶瓶まで、多種多様な器が制作されている上に、一つの形状ではなくさまざまなフォルムで展開されている。しかも、その一つ一つの作品としてのクオリティの高さ、何度も試作を重ねていくことで定まっていく機能美と装飾美を両立させたデザイン、その質に対する量の多さは、どう考えても、一人の陶芸家が生み出すことのできる範疇を超えていた。しかしながら、彼との会話の中で、制作が土岐で行われていること、彼自身が分業制による新たな焼きものの可能性を常に意識していることを聞き取ると、やはり、歴史的な背景や風土を兼ね備えた美濃という場所が村上さんを呼んだのだろう、と思わざるを得ない。きっと美濃には、量産型の生産と個人規模の生産の中間にあるような、分業制の生産を可能にする土壌があるのだろうと考えた。
土岐にある村上さんの工房へ

現代の焼きものイノベーターとも言える彼が今何を考えているのか、どのように制作を行なっているのか、その秘密は簡単には明かされずとも、そのヒントだけでも知りたくなった。以前から好きだった中国茶の話の花も咲き、彼のご厚意で、工房をカメラマンの水田秀樹さんと共に訪ねることができた。
村上さんの工房は、多治見駅から車で10分ほどの場所にある。一人で制作するには広すぎるのではないかと思われる工房の中には、再生土、地元の土、唐津の土、常滑の土、宜興(ぎこう)の朱泥、土鍋土などさまざまな陶土が積まれていて、制作する器とその目的によって土を変え、あるいは組み合わせることで最適な生地を作り出すのだという。「例えば、朱泥は土に含まれる鉄分の種類によって味が変化します。中国茶器の場合は、味が変わってくるから慎重になります。一方白磁の場合は味の変化がなく、お茶の持っている味をストレートに引き出します。」と村上さんは話す。

そんな彼が、自分個人の制作と並行しながら力を注いでいるのが、地元の業者さんの力を借りて、作家、業者、それぞれの強みを活かし合いながら分業制で茶器を量産していくプロジェクトだ。「作家ものは品質がグレーな面がありますがメーカーによる量産の品質は保証されています。そして割れてしまっても買い増せる。必然的に値段もお手頃になります。作家ものでもその辺りをクリアしたものを提供したいと思いました。」と話す彼に、技術面の不安はないのか、という質問を投げかけると「それはあります。でも、できないと思っていたことも、お互いの工夫で乗り越えられたりする。量産だから質が悪いとは限らず、むしろ、分業制にすることで質が上がることもある。中国には量産で美しいものは沢山あるけれど日本にはまだないから、それを成し遂げたい。美濃という土地にいるからこそ、それができるはず。」と熱のこもった答えが返ってきた。
陶器を作り出す陶土には恵まれていたが、磁器を制作するための陶石には伊万里のように恵まれていなかった美濃は、江戸時代の初め、陶土に珪石と長石を加え、工夫に工夫を重ねて磁器の生産に成功した歴史がある。資源や技術が足りないという状況においても、それを乗り越えるための創意工夫を重ねる精神がこの地には根付いていて、そのDNAを村上さんもまた受け継いでいるのかもしれない。

「量産に必要な技術も、完全に機械ではなく結局は職人仕事なんです。そういった技術も、人の手によって成り立っている。分業制で業者さんが器の研磨をしたり仕上げてくれるのだけれど、縁の箇所の薄さが足りない時や滑らかな形状にしたい時は、自分が仕上げたりする。それでもやっぱり、最初から最後まで自分で制作するのとは時間の掛け方が全く違う。」完全機械生産ではない焼きものの制作において、機械を使いこなすのもまた人。そして技術力とセンスが問われる。当たり前のようなことだけれど、村上さんに言われて、改めてはっとさせられた。
分業制が成功すれば、今後人材の確保と育成に繋がり、ひいては美濃の町興しに繋がるかもしれない。「そうできるように、今色々な人と知恵を出し合いながら、なんとか街を盛り上げるために奮闘している。でも、まだまだ人材は不足しているし、日本で使われる陶磁器も海外製が多くなっているし、美濃にある土を作るための工場も老朽化を迎えて設備投資が必要だし、戦後から今にかけて積もった色々な問題に直面している。10年後にどうしようか?と話しても、もう間に合わないと思う。」その話を伺って、自分が関わっていた醤油の木桶もまた絶滅危機であることを思い出す。先日伺った嬉野の茶農家さんが抱えている人材問題にも共通するところがある。日本の伝統工芸、伝統食、さまざまなものが存続か断絶か、まさに岐路に立たされている。