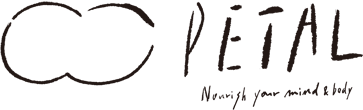2020年、晩秋。唐津を再び訪問する予定を組んでいたところ、夏には少し沈静化していたコロナウィルスが日に日に猛威をふるい始めてきた。これは真冬にどうなるか分からないぞと、急いで服をバッグに詰め込んで、飛行機に乗り込んだ。ギャラリーに器を並べる前に、もう一度作家さんの器への想いをしっかりと受け止めたかったのだ。
今回の旅で、どうしても直接お会いしたかった作家さん、それが唐津、見借という山間で作陶されている、中里花子さんだ。遡ることおよそ4年前、都内の器屋さんで偶然花子さんの器を目にする機会があり、他のどの器とも違う日本人離れした感性、それでいて自然体、唐津焼というジャンルや概念に全くとらわれることなく、花子さんの器そのものがニュージャンルのようであり、でも確実に、手に取る人の心を掴むフォルムの美しさに胸が高なったのを覚えている。

空気のように使う人の側に佇む器たち
そして4年経った今年2020年、PETALでどのような人に器を手に取って欲しいか、と考えたとき、まずは高尚な世界で使われる器ではなく、ふだんの食卓を豊かに彩ってくれる、料理を作る人や食べる人の気持ちをちょっと和やかにしてくれる器を提案したい、と考えたとき、花子さんの器が真っ先に思い浮かんだ。佐賀でお世話になっている方に相談したところ、オンラインでも良いので一度お話を伺いたい、という強引なお願いを快く引き受けて下さり、花子さんとのご縁が始まった。

暖かい日差しが入り込む、花子さんの陶房
花子さんは、人間国宝の12代中里太郎右衛門を祖父に、唐津焼の名手、中里隆を父に持ち、兄も次の唐津世代を担う陶芸家という、まさに陶芸一家のサラブレッドとして育ちながら、全く陶芸の道に興味を持たず、テニスに明け暮れる毎日を過ごしていたという。
「ずっと陶芸を避けながら、生きていました。プロテニスプレイヤーになるためにアメリカに行ったのですが、プロの道を諦めざるをえなくなったとき、さてどうしよう?他にやりたいことが見つからなかったんです。でも、アメリカから日本の文化を見直した時に、やっぱり日本の器の使い方はとってもクリエイティブだな、と。日本の器って、ダイレクトに口や肌に触れるものが多いんです。だから、視覚、触覚、器の重さ、厚み、生々しい直感、五感を呼び覚ましてくれる、世界的に見ても稀有な存在。なぜ、日本にはこういう文化が生まれ育ったんだろう?と初めて興味が生まれてきたんです。」
陶芸を避けながらも、その実「陶芸」を俯瞰からじっと眺め、異なる文化と照らし合わせることで自分なりの「焼きもの」に対する解釈を探し続け、抗えない運命に呼び戻されたかのような人生を送ってきた花子さん。
偶然にも私自身もずっとスポーツに打ち込んでいたところから、美術や演劇にのめり込んだ背景があり、花子さんの作陶スタイルが、スポーツしていた時の集中力、スピード感、リズムを活用して作られていることに、思わず深く頷いてしまう場面もあった。

陶房にはブラックボードがあり、制作予定の器のラフスケッチが描かれている
ほぼ全ての人間が、毎日一日三食ご飯と向き合う。理由もなく憂鬱な気分の時もあれば、とにかく誰かに会って話したいと思うくらい元気な時もある。カレーが食べたい日もあれば、蕎麦くらいしか啜りたくないという日もある。その日、その時の自分の気分や感情をどんな風に労りたいのか。奮い立たせたり、和やかにしたり、寄り添ってくれたりする器を、その時々で、人は自然に選んでいるのだと思う。
子育てや仕事に追われた一日、とにかく何も考えずに美味しいご飯が食べたいと思い立ち、ふと無意識に手に取っているのが、花子さんの器だ。旬の野菜を蒸して盛り付ける。ホカホカの鮭おにぎりを並べる。そんな料理が花子さんの器にはよく似合う。花子さんの器に付けられた色の名前で”ブルージーン”という色がある。あれは、まさにファッションでいうところの”ジーンズ”だと思う。どんな柄にも、どんなスタイルにも合うジーンズは、ネーミングとして見ても素晴らしい。そういうことを意図せずに生み出してしまうのが、花子さんの天性の才能を感じる所以だ。

JAZZが流れる、アットホームで素敵なギャラリー
花子さんが運営されているギャラリー”monohanako”は、”mono= Only”と”mono=もの”を組み合わせた言葉。瀬戸もの、唐津もの、そして花子もの、なのかもしれない。「用途は色々なことに使ってほしい、力まず、空気のような存在でいたい。」と話す花子さん。以前は土にこだわらなかったそうだが、最近は地元、唐津の土も使い始めていらっしゃるそう。花子さんが作ろうとしているmonoが、今後どのように変化、進化していくのか、これからもずっと見届けていきたい。
ちなみに花子さんのパートナーであるプレリーさんは、Cultivated days という日本の昔からの伝統や自然を取り入れた食文化、毎日の暮らしを記事にされている。日本人とは違った、フレッシュな視点で日本文化や芸術を軽やかに論じる文章(英文)そして美しい写真。是非ご覧になってみてください。
https://cultivateddays.co
今回の旅で、どうしても直接お会いしたかった作家さん、それが唐津、見借という山間で作陶されている、中里花子さんだ。遡ることおよそ4年前、都内の器屋さんで偶然花子さんの器を目にする機会があり、他のどの器とも違う日本人離れした感性、それでいて自然体、唐津焼というジャンルや概念に全くとらわれることなく、花子さんの器そのものがニュージャンルのようであり、でも確実に、手に取る人の心を掴むフォルムの美しさに胸が高なったのを覚えている。

そして4年経った今年2020年、PETALでどのような人に器を手に取って欲しいか、と考えたとき、まずは高尚な世界で使われる器ではなく、ふだんの食卓を豊かに彩ってくれる、料理を作る人や食べる人の気持ちをちょっと和やかにしてくれる器を提案したい、と考えたとき、花子さんの器が真っ先に思い浮かんだ。佐賀でお世話になっている方に相談したところ、オンラインでも良いので一度お話を伺いたい、という強引なお願いを快く引き受けて下さり、花子さんとのご縁が始まった。

花子さんは、人間国宝の12代中里太郎右衛門を祖父に、唐津焼の名手、中里隆を父に持ち、兄も次の唐津世代を担う陶芸家という、まさに陶芸一家のサラブレッドとして育ちながら、全く陶芸の道に興味を持たず、テニスに明け暮れる毎日を過ごしていたという。
「ずっと陶芸を避けながら、生きていました。プロテニスプレイヤーになるためにアメリカに行ったのですが、プロの道を諦めざるをえなくなったとき、さてどうしよう?他にやりたいことが見つからなかったんです。でも、アメリカから日本の文化を見直した時に、やっぱり日本の器の使い方はとってもクリエイティブだな、と。日本の器って、ダイレクトに口や肌に触れるものが多いんです。だから、視覚、触覚、器の重さ、厚み、生々しい直感、五感を呼び覚ましてくれる、世界的に見ても稀有な存在。なぜ、日本にはこういう文化が生まれ育ったんだろう?と初めて興味が生まれてきたんです。」
陶芸を避けながらも、その実「陶芸」を俯瞰からじっと眺め、異なる文化と照らし合わせることで自分なりの「焼きもの」に対する解釈を探し続け、抗えない運命に呼び戻されたかのような人生を送ってきた花子さん。
偶然にも私自身もずっとスポーツに打ち込んでいたところから、美術や演劇にのめり込んだ背景があり、花子さんの作陶スタイルが、スポーツしていた時の集中力、スピード感、リズムを活用して作られていることに、思わず深く頷いてしまう場面もあった。

ほぼ全ての人間が、毎日一日三食ご飯と向き合う。理由もなく憂鬱な気分の時もあれば、とにかく誰かに会って話したいと思うくらい元気な時もある。カレーが食べたい日もあれば、蕎麦くらいしか啜りたくないという日もある。その日、その時の自分の気分や感情をどんな風に労りたいのか。奮い立たせたり、和やかにしたり、寄り添ってくれたりする器を、その時々で、人は自然に選んでいるのだと思う。
子育てや仕事に追われた一日、とにかく何も考えずに美味しいご飯が食べたいと思い立ち、ふと無意識に手に取っているのが、花子さんの器だ。旬の野菜を蒸して盛り付ける。ホカホカの鮭おにぎりを並べる。そんな料理が花子さんの器にはよく似合う。花子さんの器に付けられた色の名前で”ブルージーン”という色がある。あれは、まさにファッションでいうところの”ジーンズ”だと思う。どんな柄にも、どんなスタイルにも合うジーンズは、ネーミングとして見ても素晴らしい。そういうことを意図せずに生み出してしまうのが、花子さんの天性の才能を感じる所以だ。

花子さんが運営されているギャラリー”monohanako”は、”mono= Only”と”mono=もの”を組み合わせた言葉。瀬戸もの、唐津もの、そして花子もの、なのかもしれない。「用途は色々なことに使ってほしい、力まず、空気のような存在でいたい。」と話す花子さん。以前は土にこだわらなかったそうだが、最近は地元、唐津の土も使い始めていらっしゃるそう。花子さんが作ろうとしているmonoが、今後どのように変化、進化していくのか、これからもずっと見届けていきたい。
ちなみに花子さんのパートナーであるプレリーさんは、Cultivated days という日本の昔からの伝統や自然を取り入れた食文化、毎日の暮らしを記事にされている。日本人とは違った、フレッシュな視点で日本文化や芸術を軽やかに論じる文章(英文)そして美しい写真。是非ご覧になってみてください。
https://cultivateddays.co