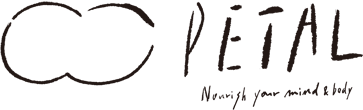唐津焼の次世代「石井義久さんを訪ねて」
Next generation of Karatsu pottery " Visiting potter Yoshihisa Ishii"
(2022.02.04)

岡本修一さんのアトリエを後にして、石井義久さんの自宅であり陶房にお邪魔することになった。石井さんは、もともと埼玉の出身でお父様が陶芸をされていて、その様子をそばで見るという幼少期を過ごした。しかし「変な癖がつくかもしれないから」と、お父様から直接教わることはなく、九州の窯業高校に進み、卒業後唐津の殿山窯で作陶する矢野直人さんを師事。2018年に独立したばかりの、今年33歳を迎える若さの唐津焼作家である。

そんな若さとは裏腹に、石井さんの作り出す唐津焼は、桃山時代の古唐津への深い愛情と探究心から、土や砂岩の特性や魅力を素直に引き出した作品が多く、土、水、火、自然そのものの持つ力を自然のままに引き出した、気を衒わない「当たり前」を大切にした器のように感じる。だからこそ、作為的ではない、無垢な魅力を湛えている。おそらく、師事されていた矢野直人さんの影響も多くあるのだろう。陶土も、暮らしている家の裏山や近所の山を自分の足で歩きながら探し、掘って持って帰ってくるのだそうだ。

「近年は、山を勝手に掘ったら怒られるし、地元の良い土をどうやって手に入れるか難しくなってきていると思うんですが、石井さんは他の地域から土を買ったりすることは考えたりしないんですか?」と訊くと「それはもう、唐津で見つけるしかないんですよね。ここの土を使えば自分の理想としている器に近づくこと、その快楽を知ってしまいましたから、それ以外は考えられない。」という返答。石井さんから頂戴した、焼酎などを楽しむための大きめのお猪口を思い浮かべた。確かに、あのしっとりとした手触り、口当たりの柔らかさは他の陶土、陶石では実現しないものだろう。快楽、という表現もまた陶芸と日々戯れるからこそ生まれた表現だろう。

「資本主義とは逆行した生活を送っています。近所の方たちが何かあるたびに、ご飯や野菜をお裾分けしてくれたり、マムシに噛まれた時も色々と世話をしてくださったり。本当にありがたいんです。」と自嘲ぎみに話す石井さんの瞳は輝き、前を向いている。貨幣や金銀といった現代の経済システムの物差しでは測れない、精神の探究から生まれる、静かな幸福が、彼の日々には溢れている。
陶芸に限らず、人間はさまざまな「写し」を幾度となく繰り返して、自分の方法論を確立していく。それは、言葉を商売にしているコピーライターの自分もそうだ。唐津焼の原点である古唐津を真似て、師匠である矢野直人さんの考えや技術を真似ながら、石井さんは黙々と模索している、その旅の途中であろう。年齢を重ね人間味が滲み出るごとに、彼の生み出す物もまた、私たちが想像もしなかったような面白い変化を遂げ、味わいを帯びていくに違いない。

岡本修一さんの器と、石井義久さんの器は、どちらも若手作家が生み出す「唐津焼」でありながら、その人が見てきたもの、学んできたもの、これから表現したいものが違うために生み出される形態も手にとる人も違うかもしれない。それくらい唐津焼には多様性があり、一言では言い尽くせない種類と技術、作家の自由がある。そこが唐津焼の面白さであり、唐津が、訪れるたびに驚きと喜びを持って、器との一期一会を楽しめる稀有な器の産地であると感じる理由である。
(文章:シャハニ千晶 / 作家訪問の写真:水田秀樹)