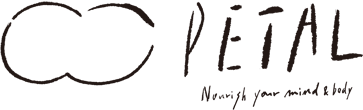さまざまな縁に導かれ、建物を引き継ぐ

夏は藤のむしろが敷かれたギャラリー
「もともとここに住んでいたお婆様が亡くなって、この建物を頼むよ、と父から言われて掃除や手直しをしていましたが、どんどん朽ちていくんです。だったらここで器を展示したりお茶を教えたりできないかと思って、42歳くらいの時に草伝社を始めました。」と語る原さん。当初は内装もタイル張りで、ボロボロだった家屋を少しずつ改装していったという。今伺っている草伝社さんの内観を拝見すると、そんな過去があったとは微塵も感じられない。淡い光の中で静かに黒唐津のようにしっとりとした光沢感を湛えた木造の空間、気持ちよく張られた畳の部屋に、庭先から清い風がすっと入りこむ。この建物もお父様も、ここに住まわれていた先人も、どんなに喜んでいるだろう。
「京都のお師匠さんに『ものづくりって見る人がいないとものは成長していかない。作家の名前や値段を見るのではなく、作家が作った”もの”を見る人が育っていかないと作家にとっては何の意味もない』と言われたことがあります。」そういった経緯もあり、草伝社さんで販売されている器の前には値段がなく、器の名だけが載った札が並んでいる。その札をひっくり返すと、作家の名前と値段がわかるのだ。つまりお客様は、一切の先入観を持たずに器に対峙することができる。若手作家も重鎮の作家も同等に並べられるのは、若手にとってはチャレンジする甲斐があるし、重鎮にとっては初心に立ち返る思いになるはずだ。「今の人は習うことばかりで教えることをしない。昔の人は命が短いから、習ったことをすぐ次の世代に教えていたんですね。だから僕は教えていかないと、と思っています。」
茶禅一味の世界とはなんだろう

作品の下に、値段と作家名が隠された札が並ぶ
草伝社を始めてすぐの頃は、唐津で作られていた茶陶は写しが多く、弟子もまた師匠の写しを見て自分も写しを始める、という流れが主流になっていたそうだ。
「正直なところ、作家さんも向付ではないものを向付としていたり、花入とは言えないものを花入と言っていたり、大変だった時期がありました。なぜ花器ではなく花入なのか。なぜ鉢ではなく向付なのか。そこの部分を理解していないまま作っている作家さんがいらっしゃった。物だけを作っていても、茶の世界におけるその物の役割を理解していないと特に茶陶は作れない。」と原さんは語る。
「ずっとお茶をしてきて僕が感じるのは、茶碗は結局、心なんじゃないかということです。千利休が作らせた黒楽茶碗は、赤みや黄みがかった黒、つまり玄色をしています。この玄というのは”空”を表しているんです。だから、自分の心を表すものが茶碗だと思っていて、だから『心を作りましょうよ』って作家さんにお伝えしています。」
確かに、長次郎も織部も先代に既にあった何かを写していたわけではない。心を表すことに全身全霊をかけて、また茶を入れるのにふさわしい全く新しい茶碗を利休とともに作り上げてきたわけだ。特に茶陶は、写しを嫌うと言われている。
草伝社という名の夢

夕方の涼しい風が庭先から入り込む
ある時、原さんはある夢を見たという。「茶事のお手伝いをする夢だったんです。それが、お手伝いをしているうちに梅の花が咲き、蝉が鳴いて、というように四季がどんどん移ろっていくんです。ここは時間の流れが早いから、ここからは自分はお暇して、自分のやるべきことをしようと考えるんです。そして、帰り際の道端でおじいさんに会って『お茶はどうだったかね』と言われて『勉強になりました』みたいな話をしていたら、おじいさんが煎茶を出してくれた。あなたが伝えるんだよ、と言われたようだった。十牛図にあるように、お茶はお客さまの悟りを開く手伝いをするために茶室に入るわけだけれど、煎茶は悟りを開いた人が市中に戻って、それを伝えていくもの。夢の中で、ああ僕はこれをやらなくちゃと思った。」
そこから原さんは、煎茶の家元を招いて煎茶教室も草伝社で定期的に開催している。
原さんは夢の話は笑われるから恥ずかしい、と仰ったが、伺っているこちらまで武者震いするような貴い話である。きっと原さんの中に草伝社という場を作るべきか、何を伝えるべきか試行錯誤があり、その彼の成し遂げたい夢の口火は、まさしく夢の中から始まったのであろう。「草を伝える」と書いて草伝社。その意味がようやく分かった気がした。

若手から巨匠と呼ばれる作家まで唐津、伊万里、有田などから幅広く唐津焼を揃える
「僕は、器を売っているという感覚があまりないんです。物はいいものを作れば人は気づいてくれる。むしろ、僕は物をさらに良くしていきたい。作家さんの方向性を少し整えて差し上げたり、そうすると自然と作家さんと歩幅が合うようになってくる。」
原さんの話と伺うと「そうだ、そういうことなのだ。」と言い知れぬ嬉しさが心の底から湧いてくる。ギャラリストとして、その前に一人の人間として心の靄が晴れて夏空が広がっていくような心情だ。
従来の常識ならば、あるギャラリーのオーナーが、別のギャラリーのオーナーを取材して紹介することは稀だろうと思う。むしろそういう交流が御法度のような匂いさえこの業界にはある。私はその点能天気とも言えるが、そういう考えとは逆側にいる人間かもしれない。原さんが仰ったように、私もまた器を売る人間というよりは、器を取り巻く精神的に豊かな世界を、面白みをただ伝えていきたい人間のひとりでありたいと願う。
帰り道の新幹線で私は、原さんがくれた問答を自分の中で反芻する。唐津は私の住む場所から決して近いとは言えないが、こんな風に美しい宿題をくれる師匠がいるから、私はまたあの場所に戻るのだと思う。

「もともとここに住んでいたお婆様が亡くなって、この建物を頼むよ、と父から言われて掃除や手直しをしていましたが、どんどん朽ちていくんです。だったらここで器を展示したりお茶を教えたりできないかと思って、42歳くらいの時に草伝社を始めました。」と語る原さん。当初は内装もタイル張りで、ボロボロだった家屋を少しずつ改装していったという。今伺っている草伝社さんの内観を拝見すると、そんな過去があったとは微塵も感じられない。淡い光の中で静かに黒唐津のようにしっとりとした光沢感を湛えた木造の空間、気持ちよく張られた畳の部屋に、庭先から清い風がすっと入りこむ。この建物もお父様も、ここに住まわれていた先人も、どんなに喜んでいるだろう。
「京都のお師匠さんに『ものづくりって見る人がいないとものは成長していかない。作家の名前や値段を見るのではなく、作家が作った”もの”を見る人が育っていかないと作家にとっては何の意味もない』と言われたことがあります。」そういった経緯もあり、草伝社さんで販売されている器の前には値段がなく、器の名だけが載った札が並んでいる。その札をひっくり返すと、作家の名前と値段がわかるのだ。つまりお客様は、一切の先入観を持たずに器に対峙することができる。若手作家も重鎮の作家も同等に並べられるのは、若手にとってはチャレンジする甲斐があるし、重鎮にとっては初心に立ち返る思いになるはずだ。「今の人は習うことばかりで教えることをしない。昔の人は命が短いから、習ったことをすぐ次の世代に教えていたんですね。だから僕は教えていかないと、と思っています。」
茶禅一味の世界とはなんだろう

草伝社を始めてすぐの頃は、唐津で作られていた茶陶は写しが多く、弟子もまた師匠の写しを見て自分も写しを始める、という流れが主流になっていたそうだ。
「正直なところ、作家さんも向付ではないものを向付としていたり、花入とは言えないものを花入と言っていたり、大変だった時期がありました。なぜ花器ではなく花入なのか。なぜ鉢ではなく向付なのか。そこの部分を理解していないまま作っている作家さんがいらっしゃった。物だけを作っていても、茶の世界におけるその物の役割を理解していないと特に茶陶は作れない。」と原さんは語る。
「ずっとお茶をしてきて僕が感じるのは、茶碗は結局、心なんじゃないかということです。千利休が作らせた黒楽茶碗は、赤みや黄みがかった黒、つまり玄色をしています。この玄というのは”空”を表しているんです。だから、自分の心を表すものが茶碗だと思っていて、だから『心を作りましょうよ』って作家さんにお伝えしています。」
確かに、長次郎も織部も先代に既にあった何かを写していたわけではない。心を表すことに全身全霊をかけて、また茶を入れるのにふさわしい全く新しい茶碗を利休とともに作り上げてきたわけだ。特に茶陶は、写しを嫌うと言われている。
草伝社という名の夢

ある時、原さんはある夢を見たという。「茶事のお手伝いをする夢だったんです。それが、お手伝いをしているうちに梅の花が咲き、蝉が鳴いて、というように四季がどんどん移ろっていくんです。ここは時間の流れが早いから、ここからは自分はお暇して、自分のやるべきことをしようと考えるんです。そして、帰り際の道端でおじいさんに会って『お茶はどうだったかね』と言われて『勉強になりました』みたいな話をしていたら、おじいさんが煎茶を出してくれた。あなたが伝えるんだよ、と言われたようだった。十牛図にあるように、お茶はお客さまの悟りを開く手伝いをするために茶室に入るわけだけれど、煎茶は悟りを開いた人が市中に戻って、それを伝えていくもの。夢の中で、ああ僕はこれをやらなくちゃと思った。」
そこから原さんは、煎茶の家元を招いて煎茶教室も草伝社で定期的に開催している。
原さんは夢の話は笑われるから恥ずかしい、と仰ったが、伺っているこちらまで武者震いするような貴い話である。きっと原さんの中に草伝社という場を作るべきか、何を伝えるべきか試行錯誤があり、その彼の成し遂げたい夢の口火は、まさしく夢の中から始まったのであろう。「草を伝える」と書いて草伝社。その意味がようやく分かった気がした。

「僕は、器を売っているという感覚があまりないんです。物はいいものを作れば人は気づいてくれる。むしろ、僕は物をさらに良くしていきたい。作家さんの方向性を少し整えて差し上げたり、そうすると自然と作家さんと歩幅が合うようになってくる。」
原さんの話と伺うと「そうだ、そういうことなのだ。」と言い知れぬ嬉しさが心の底から湧いてくる。ギャラリストとして、その前に一人の人間として心の靄が晴れて夏空が広がっていくような心情だ。
従来の常識ならば、あるギャラリーのオーナーが、別のギャラリーのオーナーを取材して紹介することは稀だろうと思う。むしろそういう交流が御法度のような匂いさえこの業界にはある。私はその点能天気とも言えるが、そういう考えとは逆側にいる人間かもしれない。原さんが仰ったように、私もまた器を売る人間というよりは、器を取り巻く精神的に豊かな世界を、面白みをただ伝えていきたい人間のひとりでありたいと願う。
帰り道の新幹線で私は、原さんがくれた問答を自分の中で反芻する。唐津は私の住む場所から決して近いとは言えないが、こんな風に美しい宿題をくれる師匠がいるから、私はまたあの場所に戻るのだと思う。