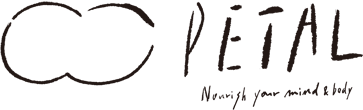漆はハレの日だけのもの?
「漆(うるし)」と聞いて、何を想像するだろうか。蒔絵に彩られたお正月のお重箱、懐石料理や和食のお店でいただく汁椀、はたまた、今流行りの金継ぎに使われる接着剤としての漆だろうか。私は、漆ときくと、祖母が大切に使っていた鎌倉彫のお盆を思い出す。塗り直しもせずに使っていたためか、盆の表面は、鮮やかな朱色も弱まり、使い込んだなめし革のような艶のある光沢が、また一つの風情となっていた。

左は新品の漆椀。右は数年使いこみ、美しい艶を纏った漆椀
漆ほど、日本人の暮らしと文化に長く深く交わりながら、現代において特に若い世代に、どのような性質のものであるのか、きちんと理解されていない工芸品もないように感じる。およそ9000年前の縄文時代の前期から、漆は鉢や壺はもちろん、武器である弓矢の先、櫛や腕輪にも使われていたと言われている。装飾だけでなく、その堅牢性、実用性、抗菌性においても、遥か昔の時代から日本人にとって漆は、万能な素材であったに違いない。彼らは身近な素材であった漆を巧みに扱い、その時代と暮らしに合わせて、姿形、使われる用途も、多様に変化させてきた。
古代は、貴族などの限られた人のみが使っていた高級漆器が、平安後期くらいから、炭粉を混ぜた柿渋の下地に変えて、工程を簡略化することで、徐々に庶民にも使われ始めていく。現代においても、ハレの日に使われる漆工芸はもちろん、暮らしの道具として日常使いされる漆器、アート表現としての漆、さまざまなジャンルにわたって、さらに漆の使われ方の自由度が増しているように思う。
どの時代においても漆は、日本人の暮らしの中で、または宗教儀式や茶道といった行為の中で重視してきた「用の美」の条件を充分に満たす貴重な存在だったのだろう。それでも、「漆って、ハレの日に使うものでしょう。」「漆って、扱い方が分からないから怖い。その上値段も高いし。」そんな声もちらほらと聴こえてくる。つまり、日常において電子レンジで料理をして、食洗機を使って洗い物をしている、時間のない現代人にとっては、なんとなく敬遠してしまう存在であることも確かなのだろう。実を言うと、つい最近まで私もその一人であった。
食器や道具としての魅力を感じながら、気軽には近づけない、そんな「漆」への印象と距離感を見事にひっくり返してくださったのが、神奈川県葉山で活動されている漆工芸作家の伏見眞樹さんである。伏見さんは、もともと横浜で育ち、鎌倉彫訓練校で学んだのち、木曽の漆工佐藤阡朗さんのもとで修行し、1987年に「伏見漆工房」を立ち上げた。40歳の私が4歳の時にすでに独立されて「漆」と向き合い、「木」の声を聴き、漆を現代に残すために制作を始められた作家である。
今年の6月、銀座にあるギャラリー「江」で伏見さん、伏見さんをご紹介してくださった佐藤智洋さんを始めとする湘南の漆作家さんたちが一同に制作した漆器作品を並べる展示会に、幸運なことに立ち会えた。黒漆、拭き漆、溜め塗り、どの漆作品も静けさを内包したような佇まいを見せながらも、一種の熱気を帯びている。その中でも、伏見さんのカトラリーを始めとする漆作品は、35年もの試作と失敗、改良を繰り返された上で導き出された、フォルムの「一つの答え」のような完成美だった。その次に私の目を釘付けにしたのは、展示会のために作られたお重だった。日本では古くから暖簾(のれん)に使われる荒めの芋麻で織られたキビラ麻を布着せさせた、初夏にふさわしい清々しく、軽やかな重箱。伏見さんは、その中に時計を入れられて展示されていて、それを見た瞬間、思わず微笑んでしまった。ハレの日の料理だけでなく、もしかしたらサンドウィッチやフルーツを入れてもいいかもしれない。時計やジュエリーのボックスとしての可能性もあるかもしれない。伏見さんのおおらかな感性を感じてワクワク、嬉しくなったのだ。

伏見眞樹さんが制作したキビラ麻を布着せした重箱にサンドウィッチを

佐藤智洋さんが制作した漆の溜め塗の汁椀に焼きなすのあんかけ
竹のカトラリー、辿り着いたデザインの境地
その数日後、伏見さんのご好意と佐藤さんのお力添えで、伏見工房に伺うことが叶った。葉山の一色は、三浦アルプスを背に、人の足跡の付いていない緑と海辺がなだらかに続く、どこか懐かしい街で大好きな場所である。工房に入るやいなや、伏見さんのさまざまな試作品、や修理中のうつわが目に飛び込み、天井に積み重ねて乾燥させている孟宗竹の香りが漂ってくる。作り手の聖域に素人が足を踏み込んだような緊張感が体に満ちてくる。
伏見さんは、新しい作品を作ることはもちろんだが、自分の作品を買われたお客様から、後々依頼される修理も、新しい作品を作ることと同じくらい大切にされている。工房にも、日本各地から送られてきた修理されるのを待つ漆の器やカトラリー、靴べらが、まだか、まだか、と美しく生まれ変わる時を待っているのだ。縄文時代の弓矢の先に使われていた漆も、何度も塗り直された跡があるという。そう考えると、漆の使い手である日本人は「サステナブル」や「エシカル」を9000年前から実践していたのだと感慨深い。
「修理に出された器を見ると、ああ、なるほど使っているとこうなるんだ、という気づきもある。」と伏見さんは言う。そんな中、伏見さんが、先端部分がボロボロになった小さなスプーンを見せてくれた。「これはベビースプーン。先を噛んで欠けたところに添え木をして修理するんです。」「修理前と後を写真に撮って差し上げて、直ったことを子どもに教えてあげる。そうすると、また大切にして使ってくれる。」と伏見さんと奥様の昌子さんは嬉しそうに話してくださった。子どもへの出産祝いで漆のスプーンを頂いたら、ほとんどの人が修理しながら、一生手元に置いておくことだろう。漆のベビースプーンは、思い出の詰まったアルバムでもあるのだ。

修理中のスプーン

ベビースプーンの修理完了時にお客様にお渡しする説明資料
伏見さんが、竹のカトラリーを作るきっかけなったのは、生漆を混ぜ合わせたり、刷り込んだりする際に使う仕事道具の、竹べらだった。「竹べらを作っていたので、竹の性質が分かっていたことが大きいですね。木は竹に比べて個体差が大きく、同じ欅の木でも、柔らかい欅と硬い欅がある。それに比べて竹は材質が均質だったんです。」と教えてくれた。そんな偶然とも必然とも言える理由から、伏見さんの代表作である竹のカトラリーが生まれた訳だが、このカトラリーを目にして手に取ると、そういった理屈が全て吹っ飛んでしまうから不思議だ。作り終えるごとに「こんなサイズで作って欲しい。」「ヨーグルト用のスプーンが欲しい。」などの要望に応えて、幅広くサイズ展開されたスプーンやフォークたち。まるでカトラリーのためにデザインされているかのような、竹の節目のアクセントが、見て直感的に美しい。それに尽きるのである。

竹のカトラリーを制作するきっかけとなった竹べら
漆を扱うコツは本当に少しだけの心遣いなのだと、伏見さんは言う。「木がびっくりして割れてしまうから、ポットから直接熱湯を入れない。」「洗った後は水切りラックなどに立てたままにせずに、さっと拭いたら横に並べて乾かしておく。そうすれば水垢が残ることもなく、逆に艶が増してくる。」「ご飯粒などがこびりついた時は、スポンジやタワシを使って強く擦るのではなく、10分ほど浸して、その後優しく洗い流す。」まるで観葉植物や樹木を育てるような漆との付き合い方。漆や木地の気持ちを少し考えれば、自然と分かることだらけだった。

スプーン制作のため、竹を彫り始める伏見眞樹さん

ずらりと並んだ伏見眞樹さんが制作した竹のカトラリー
木地づくりから下地付け、研ぎ、中塗り、上塗りまで長い工程がある中で、研ぎや拭き漆の作業を手伝う昌子さんは、伏見さんにとって公私ともにかけがえのないパートナーだ。鎌倉彫の仕事に携わっていた当時、先輩と後輩であった関係。漆のかぶれが比較的出てしまう伏見さんと、木地づくりは伏見さんのようには出来ないと感じていた奥様は、まさにお互いの強みを活かし合いながら、二人三脚で、見ても使っても唸るような漆作品を生み出し続けている。お話を伺っているうちに「お昼ご飯、ご一緒しませんか。」と優しく尋ねてくださった伏見さんと昌子さんの気遣いに触れて、自分が住まう湘南という地に、こんなにも丁寧に包み隠さず、漆の手仕事を教えてくださる先生がいることの有り難さに、あらためて心がいっぱいになった。銀座で購入し、いよいよ引き取ったお重箱を助手席に置いて、葉山の海原を脇目に車で走り抜けていくと、空っぽの重箱は、沢山の物語を詰め込んだ浦島太郎の玉手箱のようにも感じられた。
今回、ご同席くださった佐藤智洋さん、ご縁をくださった永守紋子さんに心から感謝申し上げたい。
伏見漆工房 Instagram:https://www.instagram.com/fushimiurushikobo/?hl=ja
佐藤智洋 Instagram:https://www.instagram.com/urushikobotomo/?hl=ja
永守紋子 Instagram :https://www.instagram.com/nagamoriayako/?hl=ja
「漆(うるし)」と聞いて、何を想像するだろうか。蒔絵に彩られたお正月のお重箱、懐石料理や和食のお店でいただく汁椀、はたまた、今流行りの金継ぎに使われる接着剤としての漆だろうか。私は、漆ときくと、祖母が大切に使っていた鎌倉彫のお盆を思い出す。塗り直しもせずに使っていたためか、盆の表面は、鮮やかな朱色も弱まり、使い込んだなめし革のような艶のある光沢が、また一つの風情となっていた。

漆ほど、日本人の暮らしと文化に長く深く交わりながら、現代において特に若い世代に、どのような性質のものであるのか、きちんと理解されていない工芸品もないように感じる。およそ9000年前の縄文時代の前期から、漆は鉢や壺はもちろん、武器である弓矢の先、櫛や腕輪にも使われていたと言われている。装飾だけでなく、その堅牢性、実用性、抗菌性においても、遥か昔の時代から日本人にとって漆は、万能な素材であったに違いない。彼らは身近な素材であった漆を巧みに扱い、その時代と暮らしに合わせて、姿形、使われる用途も、多様に変化させてきた。
古代は、貴族などの限られた人のみが使っていた高級漆器が、平安後期くらいから、炭粉を混ぜた柿渋の下地に変えて、工程を簡略化することで、徐々に庶民にも使われ始めていく。現代においても、ハレの日に使われる漆工芸はもちろん、暮らしの道具として日常使いされる漆器、アート表現としての漆、さまざまなジャンルにわたって、さらに漆の使われ方の自由度が増しているように思う。
どの時代においても漆は、日本人の暮らしの中で、または宗教儀式や茶道といった行為の中で重視してきた「用の美」の条件を充分に満たす貴重な存在だったのだろう。それでも、「漆って、ハレの日に使うものでしょう。」「漆って、扱い方が分からないから怖い。その上値段も高いし。」そんな声もちらほらと聴こえてくる。つまり、日常において電子レンジで料理をして、食洗機を使って洗い物をしている、時間のない現代人にとっては、なんとなく敬遠してしまう存在であることも確かなのだろう。実を言うと、つい最近まで私もその一人であった。
食器や道具としての魅力を感じながら、気軽には近づけない、そんな「漆」への印象と距離感を見事にひっくり返してくださったのが、神奈川県葉山で活動されている漆工芸作家の伏見眞樹さんである。伏見さんは、もともと横浜で育ち、鎌倉彫訓練校で学んだのち、木曽の漆工佐藤阡朗さんのもとで修行し、1987年に「伏見漆工房」を立ち上げた。40歳の私が4歳の時にすでに独立されて「漆」と向き合い、「木」の声を聴き、漆を現代に残すために制作を始められた作家である。
今年の6月、銀座にあるギャラリー「江」で伏見さん、伏見さんをご紹介してくださった佐藤智洋さんを始めとする湘南の漆作家さんたちが一同に制作した漆器作品を並べる展示会に、幸運なことに立ち会えた。黒漆、拭き漆、溜め塗り、どの漆作品も静けさを内包したような佇まいを見せながらも、一種の熱気を帯びている。その中でも、伏見さんのカトラリーを始めとする漆作品は、35年もの試作と失敗、改良を繰り返された上で導き出された、フォルムの「一つの答え」のような完成美だった。その次に私の目を釘付けにしたのは、展示会のために作られたお重だった。日本では古くから暖簾(のれん)に使われる荒めの芋麻で織られたキビラ麻を布着せさせた、初夏にふさわしい清々しく、軽やかな重箱。伏見さんは、その中に時計を入れられて展示されていて、それを見た瞬間、思わず微笑んでしまった。ハレの日の料理だけでなく、もしかしたらサンドウィッチやフルーツを入れてもいいかもしれない。時計やジュエリーのボックスとしての可能性もあるかもしれない。伏見さんのおおらかな感性を感じてワクワク、嬉しくなったのだ。


竹のカトラリー、辿り着いたデザインの境地
その数日後、伏見さんのご好意と佐藤さんのお力添えで、伏見工房に伺うことが叶った。葉山の一色は、三浦アルプスを背に、人の足跡の付いていない緑と海辺がなだらかに続く、どこか懐かしい街で大好きな場所である。工房に入るやいなや、伏見さんのさまざまな試作品、や修理中のうつわが目に飛び込み、天井に積み重ねて乾燥させている孟宗竹の香りが漂ってくる。作り手の聖域に素人が足を踏み込んだような緊張感が体に満ちてくる。
伏見さんは、新しい作品を作ることはもちろんだが、自分の作品を買われたお客様から、後々依頼される修理も、新しい作品を作ることと同じくらい大切にされている。工房にも、日本各地から送られてきた修理されるのを待つ漆の器やカトラリー、靴べらが、まだか、まだか、と美しく生まれ変わる時を待っているのだ。縄文時代の弓矢の先に使われていた漆も、何度も塗り直された跡があるという。そう考えると、漆の使い手である日本人は「サステナブル」や「エシカル」を9000年前から実践していたのだと感慨深い。
「修理に出された器を見ると、ああ、なるほど使っているとこうなるんだ、という気づきもある。」と伏見さんは言う。そんな中、伏見さんが、先端部分がボロボロになった小さなスプーンを見せてくれた。「これはベビースプーン。先を噛んで欠けたところに添え木をして修理するんです。」「修理前と後を写真に撮って差し上げて、直ったことを子どもに教えてあげる。そうすると、また大切にして使ってくれる。」と伏見さんと奥様の昌子さんは嬉しそうに話してくださった。子どもへの出産祝いで漆のスプーンを頂いたら、ほとんどの人が修理しながら、一生手元に置いておくことだろう。漆のベビースプーンは、思い出の詰まったアルバムでもあるのだ。


伏見さんが、竹のカトラリーを作るきっかけなったのは、生漆を混ぜ合わせたり、刷り込んだりする際に使う仕事道具の、竹べらだった。「竹べらを作っていたので、竹の性質が分かっていたことが大きいですね。木は竹に比べて個体差が大きく、同じ欅の木でも、柔らかい欅と硬い欅がある。それに比べて竹は材質が均質だったんです。」と教えてくれた。そんな偶然とも必然とも言える理由から、伏見さんの代表作である竹のカトラリーが生まれた訳だが、このカトラリーを目にして手に取ると、そういった理屈が全て吹っ飛んでしまうから不思議だ。作り終えるごとに「こんなサイズで作って欲しい。」「ヨーグルト用のスプーンが欲しい。」などの要望に応えて、幅広くサイズ展開されたスプーンやフォークたち。まるでカトラリーのためにデザインされているかのような、竹の節目のアクセントが、見て直感的に美しい。それに尽きるのである。

漆を扱うコツは本当に少しだけの心遣いなのだと、伏見さんは言う。「木がびっくりして割れてしまうから、ポットから直接熱湯を入れない。」「洗った後は水切りラックなどに立てたままにせずに、さっと拭いたら横に並べて乾かしておく。そうすれば水垢が残ることもなく、逆に艶が増してくる。」「ご飯粒などがこびりついた時は、スポンジやタワシを使って強く擦るのではなく、10分ほど浸して、その後優しく洗い流す。」まるで観葉植物や樹木を育てるような漆との付き合い方。漆や木地の気持ちを少し考えれば、自然と分かることだらけだった。


木地づくりから下地付け、研ぎ、中塗り、上塗りまで長い工程がある中で、研ぎや拭き漆の作業を手伝う昌子さんは、伏見さんにとって公私ともにかけがえのないパートナーだ。鎌倉彫の仕事に携わっていた当時、先輩と後輩であった関係。漆のかぶれが比較的出てしまう伏見さんと、木地づくりは伏見さんのようには出来ないと感じていた奥様は、まさにお互いの強みを活かし合いながら、二人三脚で、見ても使っても唸るような漆作品を生み出し続けている。お話を伺っているうちに「お昼ご飯、ご一緒しませんか。」と優しく尋ねてくださった伏見さんと昌子さんの気遣いに触れて、自分が住まう湘南という地に、こんなにも丁寧に包み隠さず、漆の手仕事を教えてくださる先生がいることの有り難さに、あらためて心がいっぱいになった。銀座で購入し、いよいよ引き取ったお重箱を助手席に置いて、葉山の海原を脇目に車で走り抜けていくと、空っぽの重箱は、沢山の物語を詰め込んだ浦島太郎の玉手箱のようにも感じられた。
今回、ご同席くださった佐藤智洋さん、ご縁をくださった永守紋子さんに心から感謝申し上げたい。
伏見漆工房 Instagram:https://www.instagram.com/fushimiurushikobo/?hl=ja
佐藤智洋 Instagram:https://www.instagram.com/urushikobotomo/?hl=ja
永守紋子 Instagram :https://www.instagram.com/nagamoriayako/?hl=ja