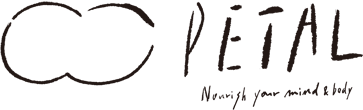暮らしの竹、うるわしの竹 別府の竹細工を訪ねて vol.1
Practical but Beautiful -Japanese Bamboo crafts- vol.1
(2024.06.02)
▪︎竹細工との再会

数年前に鎌倉に住み始めた私は、鎌倉山一帯に生えている竹の多さに驚いた記憶がある。最初は風光明媚だなあ、鎌倉らしいなあと感じていたのだが、どうやらそんな綺麗事だけではないことをその後に知ることになった。
植木職人の知人から聞いた話によると、日本の竹林は大変な課題を抱えているらしいということだった。1950年代に増え続け管理されていた竹林はプラスチック資源や輸入たけのこの登場とともに徐々に使われなくなり、今では「放置竹林」と呼ばれ、その一帯は日本中で増え続けているという。一本植えると増え続ける竹の生命力は、現代では仇になっているというわけだ。人間の勝手な事情で植えた竹なのに、人間の手に負えなくなっている。なんとも現代人らしい、ちょっぴり情けない話だ。
私にとっての「竹」という素材もまた、あまりにも普遍的に自分の暮らしと共にあったものだ。祖母の白湯を入れる籠が竹で編まれていたり、竹ざるでお蕎麦やおにぎりを頂いたりしたものだ。農業を生業としている家庭ならば、万石(米揚げざる)や野菜籠とは無縁ではないだろう。道具として大いに活躍してきた竹はその姿のとおり日本人の暮らしの支柱であり続け、この国の文化を四方から編み続けてきた。 空気のような存在の竹に、私自身は立ち止まって自分の眼を凝らす機会に巡り会えなかったように思う。ギャラリーで見かける高級感のある「竹細工」から雑貨屋さんで目にするアジア製の竹籠まで、種類、品質、技法、時代によって大きく姿を変えていく捉えどころがない竹の世界に戸惑いさえ感じていた。

後藤さんが製作したお出掛け籠
そんな私に、竹細工の世界に一歩踏み入れるきっかけをくださったのが後藤洋司(ごとうひろし)さんだった。ある盛岡でのイベントで後藤さんが偶然ご自分の制作した竹の水切り籠や六ツ目おでかけ籠を展示されていた。そこに盛岡に住んでいるおばあちゃまが近づいて、「あら、竹籠ねえ。昔はこの辺りも籠屋さんがいたよ。竹籠を売って歩いていたもんだ。」と話しかけている。その話の内容が面白くてつい聞き耳を立ててしまった。後藤さんの話しを伺いながら私は生まれて初めて、そこでじっくりと竹と向き合った。理屈云々ではなく、後藤さんの作る竹籠は質実でありながら年を追うごとに美しくなる片鱗をふんだんに感じさせた。後藤さんの熱意ある語り口もあり色々と話し込んでいるうちに、「竹細工」をもっと理解したい、何か力になれることはないだろうか、と素直に感じることができた。
竹細工を紹介するからには、まずは竹にどっぷりと浸からなくてはと思った。後藤さんが製作している別府を訪れてみたいことを伝えて、約束通り今年の春に別府に伺うことが叶ったのである。

別府の山あいの風景。この辺りには竹林が多く残っており製作が追いつかないほどである。
▪︎精神の拠り所としての竹

工房やカフェなどに再活用されている大津留交流センター
後藤さんとは別府駅で落ち合ったのだが、彼の工房はそこから車で40分ほどの大津留交流センターにある。この場所は廃校となった小学校を利用して、部屋の貸し出しやコミュニティーに役立てられているという。この地域で製作していた竹細工職人(阿部功一さん・三原啓資さん)が数年前に入居したのをきっかけに、次第に人が集まりはじめ、今ではこの地域の竹細工の拠点のような存在になっている。
「竹細工を製作するのは、細長くて突っ掛かりのない場所が必要なんです。製作している時に、長い竹が床に引っ掛かるとやりにくいんですよね。そういった意味では学校の廊下っていうのは理想的な場所です。」と後藤さんが笑いながら教えてくれた。なるほど、陶芸や他の工芸と違って、竹細工というのは籠を編む場所、籠を置く広めの場所が必要となる。昔は家の中ではなく外で作業していたというのもうなずける。

後藤さんが製作した竹籠や収集した世界の竹細工。
後藤さんはもともとはニュージーランドなど長く海外を旅していたという。「旅をする中で、自然とともに暮らす人々に興味が湧き、大学卒業後に山の中に暮らしたいという思いから、ジビエに関わる仕事をしていました。でもそんな日々が続いていたある日、イノシシがお金に見えてしまって。これは何かが違うな、と思って他の生き方を探しているときに”竹細工”という在り方に出会ったんです。」と語る。自分の技術そして竹林があれば、日本中のどこでも編める竹細工に関心を持ち大分県立竹工芸訓練センターに入学。2年間の勉強を終えて制作活動に入ったという。
大津留交流センターの教室、後藤さんの工房には、今回展示に参加してくださる青柳慶子さんや彼らの先輩である遠藤元さん、後輩の伊藤日向子さんが集まってくださった。後藤さんが竹籠にポットとお湯呑みと和菓子を入れてきてくださり、ちょうど自分がお土産として持参したクッキーもあり、思いがけない愉しいお茶会となった。作家それぞれの竹細工の世界に入った理由は実にさまざまだったが、とても印象的だったのは最初から「竹細工を目指して」そこに来た人は一人もおらず「たどり着いたのが竹だった」という、それぞれの作家自身の人生における哲学的な自問自答があるということだった。

竹細工作家の後藤洋司さん、青柳慶子さん、伊藤日向子さん
「竹は家業として継ぐ方も多いけれど、僕のように人生に紆余曲折あって、竹に行き着く方も多いんです。」
後藤さんのその一言は、私にとってはとても新鮮に感じられた。それは、自分が先入観として抱いていた日本の伝統工芸としての竹細工というより、精神の拠り所としての竹であり、パーソナルでありながら手触りのある物語のようで、すとんと腑に落ちたのである。「手を動かすことが好き」「街で働くことに興味が持てない」「人と話すことが苦手だった」「自然の中で暮らしたい」そう感じて辿り着いた人たちと竹細工の関係はまさしく持ちつ持たれつであり、作家自身の心のあり方を支えているようにも感じられる。こういった人間の精神と自然を繋ぎとめる職業は昔は沢山あったのだろうが、今見渡せば限りなく少ない。しかしながら、これからの時代に人間が人間であるために、絶対的に必要とする活動の一つだろうと思う。

作家それぞれが製作した竹籠。経年変化した竹籠はどれも美しい。

数年前に鎌倉に住み始めた私は、鎌倉山一帯に生えている竹の多さに驚いた記憶がある。最初は風光明媚だなあ、鎌倉らしいなあと感じていたのだが、どうやらそんな綺麗事だけではないことをその後に知ることになった。
植木職人の知人から聞いた話によると、日本の竹林は大変な課題を抱えているらしいということだった。1950年代に増え続け管理されていた竹林はプラスチック資源や輸入たけのこの登場とともに徐々に使われなくなり、今では「放置竹林」と呼ばれ、その一帯は日本中で増え続けているという。一本植えると増え続ける竹の生命力は、現代では仇になっているというわけだ。人間の勝手な事情で植えた竹なのに、人間の手に負えなくなっている。なんとも現代人らしい、ちょっぴり情けない話だ。
私にとっての「竹」という素材もまた、あまりにも普遍的に自分の暮らしと共にあったものだ。祖母の白湯を入れる籠が竹で編まれていたり、竹ざるでお蕎麦やおにぎりを頂いたりしたものだ。農業を生業としている家庭ならば、万石(米揚げざる)や野菜籠とは無縁ではないだろう。道具として大いに活躍してきた竹はその姿のとおり日本人の暮らしの支柱であり続け、この国の文化を四方から編み続けてきた。 空気のような存在の竹に、私自身は立ち止まって自分の眼を凝らす機会に巡り会えなかったように思う。ギャラリーで見かける高級感のある「竹細工」から雑貨屋さんで目にするアジア製の竹籠まで、種類、品質、技法、時代によって大きく姿を変えていく捉えどころがない竹の世界に戸惑いさえ感じていた。

そんな私に、竹細工の世界に一歩踏み入れるきっかけをくださったのが後藤洋司(ごとうひろし)さんだった。ある盛岡でのイベントで後藤さんが偶然ご自分の制作した竹の水切り籠や六ツ目おでかけ籠を展示されていた。そこに盛岡に住んでいるおばあちゃまが近づいて、「あら、竹籠ねえ。昔はこの辺りも籠屋さんがいたよ。竹籠を売って歩いていたもんだ。」と話しかけている。その話の内容が面白くてつい聞き耳を立ててしまった。後藤さんの話しを伺いながら私は生まれて初めて、そこでじっくりと竹と向き合った。理屈云々ではなく、後藤さんの作る竹籠は質実でありながら年を追うごとに美しくなる片鱗をふんだんに感じさせた。後藤さんの熱意ある語り口もあり色々と話し込んでいるうちに、「竹細工」をもっと理解したい、何か力になれることはないだろうか、と素直に感じることができた。
竹細工を紹介するからには、まずは竹にどっぷりと浸からなくてはと思った。後藤さんが製作している別府を訪れてみたいことを伝えて、約束通り今年の春に別府に伺うことが叶ったのである。

▪︎精神の拠り所としての竹

後藤さんとは別府駅で落ち合ったのだが、彼の工房はそこから車で40分ほどの大津留交流センターにある。この場所は廃校となった小学校を利用して、部屋の貸し出しやコミュニティーに役立てられているという。この地域で製作していた竹細工職人(阿部功一さん・三原啓資さん)が数年前に入居したのをきっかけに、次第に人が集まりはじめ、今ではこの地域の竹細工の拠点のような存在になっている。
「竹細工を製作するのは、細長くて突っ掛かりのない場所が必要なんです。製作している時に、長い竹が床に引っ掛かるとやりにくいんですよね。そういった意味では学校の廊下っていうのは理想的な場所です。」と後藤さんが笑いながら教えてくれた。なるほど、陶芸や他の工芸と違って、竹細工というのは籠を編む場所、籠を置く広めの場所が必要となる。昔は家の中ではなく外で作業していたというのもうなずける。

後藤さんはもともとはニュージーランドなど長く海外を旅していたという。「旅をする中で、自然とともに暮らす人々に興味が湧き、大学卒業後に山の中に暮らしたいという思いから、ジビエに関わる仕事をしていました。でもそんな日々が続いていたある日、イノシシがお金に見えてしまって。これは何かが違うな、と思って他の生き方を探しているときに”竹細工”という在り方に出会ったんです。」と語る。自分の技術そして竹林があれば、日本中のどこでも編める竹細工に関心を持ち大分県立竹工芸訓練センターに入学。2年間の勉強を終えて制作活動に入ったという。
大津留交流センターの教室、後藤さんの工房には、今回展示に参加してくださる青柳慶子さんや彼らの先輩である遠藤元さん、後輩の伊藤日向子さんが集まってくださった。後藤さんが竹籠にポットとお湯呑みと和菓子を入れてきてくださり、ちょうど自分がお土産として持参したクッキーもあり、思いがけない愉しいお茶会となった。作家それぞれの竹細工の世界に入った理由は実にさまざまだったが、とても印象的だったのは最初から「竹細工を目指して」そこに来た人は一人もおらず「たどり着いたのが竹だった」という、それぞれの作家自身の人生における哲学的な自問自答があるということだった。

「竹は家業として継ぐ方も多いけれど、僕のように人生に紆余曲折あって、竹に行き着く方も多いんです。」
後藤さんのその一言は、私にとってはとても新鮮に感じられた。それは、自分が先入観として抱いていた日本の伝統工芸としての竹細工というより、精神の拠り所としての竹であり、パーソナルでありながら手触りのある物語のようで、すとんと腑に落ちたのである。「手を動かすことが好き」「街で働くことに興味が持てない」「人と話すことが苦手だった」「自然の中で暮らしたい」そう感じて辿り着いた人たちと竹細工の関係はまさしく持ちつ持たれつであり、作家自身の心のあり方を支えているようにも感じられる。こういった人間の精神と自然を繋ぎとめる職業は昔は沢山あったのだろうが、今見渡せば限りなく少ない。しかしながら、これからの時代に人間が人間であるために、絶対的に必要とする活動の一つだろうと思う。