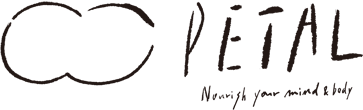唐津の心を映し出す場所
唐津に行くたび、時間が許す限りお目にかかりたい方がいる。茶道に使われるお茶菓子などの和菓子の作り手をしながら器のギャラリー「草伝社」をされている原 和志さんもその一人だ。
唐津駅から車を10分ほど走らせると北波多という地域がある。公民館などがある住宅地の一角をふらりと入ると、ゆうに100年は超えるであろう、切妻屋根の美しい古い家屋が現れる。入り口に吊られた生成り色の暖簾がゆらゆらと風に揺れている。私が唐津に来て「ああ、無事に唐津に来られたなあ。」と一番ほっとする瞬間だ。
2年前の秋、初めて唐津を伺ったおりに、案内役のYさんに器作家さんを訪ねるスケジュールを組んでいただいた。「まずは草伝社さんに行きましょう。」と言われて、連れていって頂いたのが最初の訪問だった。その時は「なぜ、器作家さんを訪ねるというのに、最初に器のギャラリーを伺うのだろう?」と少し不思議な気持ちがした。しかし今となっては、唐津に器を目当てに来られる方を、私も真っ先にお連れするのは草伝社さんだろうと思う。いや、器好きな方ばかりではない、器の向こう側にある「唐津の心」を垣間見るには、草伝社さんは絶好の場所なのではないだろうか。
何度か草伝社さんを訪問していて、ふと気がついたこと。原さんにはいつも、現地の作家さんのお考えになっていること、ギャラリストとしての矜持(深刻なものではなく)、そして彼の言葉の断片から感じられる和敬清寂の眼差し、軽妙な冗談などを笑いあっているとあっという間に時間が過ぎる。原さんは謙虚でご自分のことをあまりお話しにならないので、彼の生い立ちや考えを聞けずじまいに終わってしまうのだ。鎌倉に戻ると、「ああ、もっと聞いておけばよかった」と後悔と未練が私の頭をもたげる。そんな未練が積み重なったこともあり、今回原さんご自身のお話を伺う時間をいただいた。
人生を変えた、一輪の花

小さい頃からお花が好きだった原さん。将来はお花屋さんになりたいと考え、専攻していた学部で学んでいた地質調査とは別に、大学時代の4年間お花屋にアルバイトとして勤めていた。ところがある日、地質調査で山に登った時にすずめ蜂に追いかけられ、川に入り向こう岸まで渡って、なんとか逃げたという。ずぶ濡れになり汗だくになって、ようやく呼吸を落ち着かせてふと前を見ると、息をのむほど美しい白い花がたった一輪、自分の目の前に咲いていたのだそうだ。
「たった一輪の花の美しさが頭から離れず、自分が求めていたのは作られたものや花屋で何百円で切り売りされる花ではなく、そこに咲いている花なのだということに気づいたんです。」と原さんは教えてくれた。
大学を卒業後、東京で花屋への就職をやめて唐津に戻った彼は、地質調査での経験を活かして、吉野ヶ里や名護屋城博物館などで文化財の調査に関わり、唐津焼や有田焼の陶片などを元に復元図の作成を行なっていた。海外へ行く機会もあり「日本の文化とは何か」と訊かれたことがきっかけで、その頃からお茶の勉強も始めたそうだ。しかし、その後に入った役所で人生を変える出来事が起こる。「文化財の仕事をするために役所に入ったのですが、職場環境や人間関係に悩んでしまったのです。そんな体験を経て、自ら何かを立ち上げようと決めました。」
お茶が好きで、花が好き。学んでいたお茶の周辺で自分にできることはないか、と考えたときに「菓子」という存在に出会ったという。「春夏秋冬の季節を表現することもできるし、その時代の文化を映し出すこともできる。また唐津には、京都や金沢のようにお茶の文化があるのに菓子の文化があまりない。唐津でお茶をしていると菓子屋がない、という声もきいていたので、それじゃあやろうかと思いました。最初は御饅頭しか作れなかったんですよ。」と原さんは笑いながら話す。

しかしその当時、唐津ではお茶碗で言えば個展で見栄えのするようなフリーカップが多く、作家性が前に出すぎて、お茶席で使える茶碗や菓子が活きるような器が唐津にはなかなか見つからなかったそうだ。「お茶の世界でも茶碗や花が、自分が自分が、と主張しすぎるとくどくなる気がしていて。日本の美しさって、野趣でもなく、かといって手を入れすぎるわけでもない、それぞれがお互いに一歩ずつ下がることによって、全体の調和を保とうとするんですよね。」
お茶の世界における調和を考えた時に花や菓子のみならず、器を取り扱うようになったというのも、とても自然な流れとも言える。今の時代において、お点前という形にとらわれず、掛け軸や茶碗、菓子、懐石の値打ちにとらわれず、無垢な気持ちでもてなす澄んだ心を反映させながら、茶事を一通りできる人が一体どれほどいるだろう。
後半へ続く